『ビフォーとアフターが一目でわかる 発明が変えた世界史』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『ビフォーとアフターが一目でわかる 発明が変えた世界史』です。
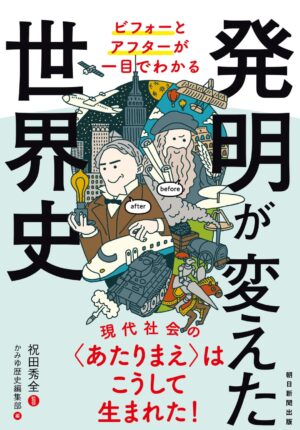
1 読んだら役に立つと思われる人
・発明の歴史をを知りたい人
・発明はどんな価値を生んだのか知りたい人
・日常がどんな発明に支えられていのかを知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①紙の進化を感じられたこと
②発明が社会に役立つまでの流れを感じられたこと
③自分の求める予想していた結果と違っていたことへの興味の大切さ
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
発明によって何が変わっていくのか?
興味を持ったので読んで見ることにしました。
4 本を使っての変化
この本を読んで大きく3つの変化がありました。
まず、1つ目は、
紙の進化を通じて価値の進化を知れたことです。
文字を記録するものの歴史は、
粘土板、パピルス、羊皮紙・・・重く、高価、作るのが大変
↓
紙・・・書きやすい、軽い、安価
この変化だけで
・軽量化
・作成工程の簡易化
・使いやすさ
・安さ
の価値が生まれたことを感じられます。
これ以外には誰にでも使えることも大きな価値でしょう。
文字が分かっていれば、書けるものがあれば誰にでも書くことができます。
使える人が多いから成功したものとしては、
思い浮かぶのはMicrosft Officeです。
電子データのフォーマットとして使える人が多いので、
電子上の紙といってもいいかもしれません。
電子化によって完全に物理的な重さはなくなり、
体積もなくなったので物理的なコストもなくなりました。
文字を記録するものを紙とするなら、
概念としての紙はどんな進化をするのか楽しみです。
(可能性の1つとして、そのうち自動翻訳によって新たにどの国の言葉でもない
世界共通語へ変換することで各言語への翻訳作業がなくなるかもしれません。⦆
2つ目は、
発明が社会に役立つまでの流れを知れたことです。
発明が成功したとします。
それを社会に役立てるとなると
・値段は?
・使う人は?
・どういう時に使うのか?
・どうやって使うのか?
・簡単に使えるのか?
これらを改良しながら社会に広める段階が必要になります。
発明があること自体を知ってもらわなければ、
どんなに良いものであっても社会に役立つことはありません。
発明ができるか?できないか?
だけでなくそれをどう社会に役立てるかも一緒に考えておくことが、
発明者の社会的成功につながっていることを感じました。
最後の3つ目は、
自分の求める予想していた結果と違っていたことへの興味の大切さです。
この本のペニシリン(抗生物質の代表例)の項目で、
実験に使う細菌を培養したところ、アオカビが発生。
しかし、よく見るとアオカビの周囲だけ細菌が繁殖していませんでした。
こうして、アオカビから細菌を殺す物質ペニシリンが発見されました。
と書かれています。
こうしたうっかりやってしまったことにも、
ただ失敗として流すのではなく新しく起こったこととして、
起きた出来事に純粋に向き合うことが大切であると感じました。
いつも通りいつもと同じでは、
違いによる新しく考えるチャンスを逃していて
もったいいないと考えるようになりました。
全体的な感想としては、
日頃自分が何気なく使っているものにどんな価値があるのか気がついた1冊でした。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『ビフォーとアフターが一目でわかる 発明が変えた世界史』を使ってみてはいかがでしょうか?