『日本の神様解剖図鑑』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『日本の神様 解剖図鑑』です。
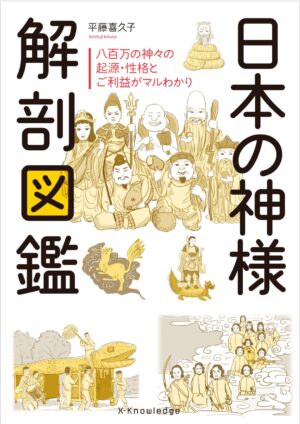
1 読んだら役に立つと思われる人
・日本の神様について知りたい人
・仏教が日本の神様に与えた影響を知りたい人
・日本の神話を通して古くからある日本の考え方を知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①仏教が神様に与えた影響に触れられたこと
②たたり神も祀ればよくなる考え
③ものもひとも神になる考え
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
古事記の本を以前に読んだことがあったので、
改めて日本の神様について考えてみることにしました。
4 本を使っての変化
この本を読んで大きく3つの変化がありました。
まず、1つ目は、
仏教が神様に与えた影響について知れたことです。
古代においては、神は自然に降るものとされ、
特定の場所に常在する社殿(本殿)はなかった。
神道の世界に社殿が設けられたのは、
6世紀に仏教が伝来の影響を受けたからだそうです。
ということは、
今の神社があるのは仏教のお寺があったおかげということ。
仏教が来るまでの神様を想像すると
神社がないので人々の神様の考えたは自由だったように思いました。
今は神様と神社が結びついていることで、
逆に神社以外で神様を感じることが難しくなっている気がしました。
目に見えるようにわかりやすく視覚化することで、
視覚化されていない部分の可能性を見過ごしていないかを考えさせられました。
2つ目は、
祟り神も祀れば良い神になる考え方に触れられたことです。
祟り神として一番有名なのおそらく菅原道真でしょう。
平安時代の政争に敗れ最終的に九州の大宰府で亡くなることになります。
その後、政争の相手が亡くなったり、清涼殿に雷が落ちたり、
それを目撃した天皇が崩御したりと悪いことが続き、
これを菅原道真の怨霊が原因と京都の北野天満宮に神として祀られるようなりました。
自分と敵対する相手を滅ぼすのではなく、
大切にすることで味方にするというのは、
これからもずっと残り続けて欲しい考えだと思いました。
最後の3つ目は、
ものも人も神になる考えに触れられたことです。
古道具が付喪神になったり、人が神になったりと、
神様はもともといるもの以外に神様にる考えは、
思考の自由さを与えてくれているように思います。
付喪神からはものを大切にすること、
人が神様になることについてはその時代に必要なことすること、
そうした日々の積み重ねが1つの結果として
神になるそういわれているように感じました。
全体的な感想としては、
日本の神様を通じてもともと日本は多様性を持っている国だと感じる1冊でした。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『日本の神様 解剖図鑑』を使ってみてはいかがでしょうか?