『荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方』です。
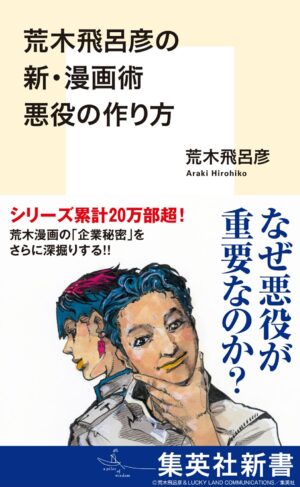
1 読んだら役に立つと思われる人
・漫画を描きたい人
・前作の『荒木飛呂彦の漫画術』を読んでいる人
・荒木飛呂彦先生の考え方を知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①前向きであることの大切さを感じられたこと
②「融合」という見方を知れたこと
③悪役について考えられたこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
前作の『荒木飛呂彦の漫画術』を読んでいて、
今回はどんなことを書いているのか興味を持ったので読んでみることにしました。
4 本を使っての変化
この本を読んで大きく3つの変化がありました。
まず、1つ目は、
常に前向きであることを改めて感じられたことです。
この本の中で荒木先生の主人公と悪役の共通点として、
どちらもとにかく前向きに生きていることがあげられています。
悪役と前向きの違和感がありましたが、
なるほど悪役となってはいるが悪役自身は、
自分の世界を良くするために行動しているだけなので
前向きと表現することもありなのだと考えなおしました。
たとえ方向性が違ったとしても、
前向きに行動すること自体が魅力になるのだ思いました。
2つ目は、
「融合」という見方を知れたことです。
この本の中で
“自然界にあるものは皆「融合」するようにつながっていて、
すべてが溶け合い、しっくりハマっています”(P8)
と書かれています。
そこから漫画の中で違和感を感じるのなら、
・何かが間違っている
・何かを知らない
・何かが足りない
・よけいなものがある
と話が展開していきます。
これは漫画だけに限らず普段のものの見方として面白いのではと思いました。
これを日常的にするのだとすれば、
見の回りにあるものをきちんと認識して、
・それがそこになぜあるのか?
・人によるものなのか?自然によるものなのか?
・人が持っているものからどんなものが好きなのか?
など今まで何も考えていなかったところに
世界は広がっているように感じました。
最後の3つ目は、
悪役について考えられたことです。
本の中で主人公と悪役はセットで考え
主人公と悪役は互いのキャラクターを引き立てるものしています。
これを日常生活に役立てるとしたら、
自分が何かをした時にそれを邪魔する人が現れた場合、
仮想悪役にしてみることのように思います。
仮想悪役といっても、
自分が正しい、相手が間違っているというスタンスではなく、
自分のどこと相手のどこが違っているのか?
自分の中の価値観を見つける鏡として
使ってみるのが面白いように感じました。
そう考えると自分の価値観を広げたいのであれば、
新しい人と話すことが1つの大きな方法なのだと改めて思いました。
全体的な感想としては、
荒木飛呂彦先生が漫画を描き続けられているのは、
好奇心を持ち物事にきちんと向き合ってきたからなのだと思う1冊でした。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方』を使ってみてはいかがでしょうか?