『脳科学は人格を変えられるか?』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『脳科学は人格を変えられるか?』です。
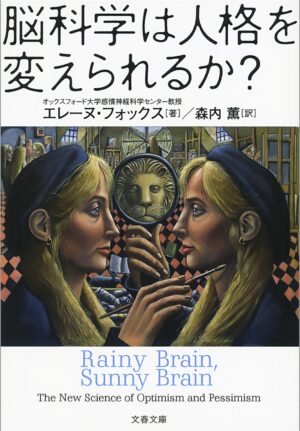
1 読んだら役に立つと思われる人
・性格についての遺伝子と環境の関係を知りたい人
・ポジティブに考えることによる科学的な変化について知りたい人
・ポジティブな脳の働きとネガティブの脳の働きについて知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①楽観について考えられたこと
②性格についての遺伝子と環境の考え方が深くなったこと
③ポジティブとネガティブの黄金比を知れたこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
前回、前々回に引き続き以前に使った『知的戦闘力を高める 独学の技法』で紹介されて、
興味を持ったので読んでみることにしました。
4 本を使っての変化
この本を読んで大きく3つの変化がありました。
まず、1つ目は、
楽観についての考え方が変わったことです。
この本を読むまでの私の楽観は、
特に根拠も何の努力もせずうまくいくと思っていると認識していたようで、
無責任な考えだと思いどこか好きになれないでいました。
この本の中で紹介されている楽観を私なりに要約すると、
①嫌なことも起こることをきちんと受け止める
②嫌なことにも自分が影響を与えることができると思って行動する
③最終的にはうまくと信じている
①をしないと見ないふりをして終わってしまいます。
②が自分が影響を与えられないと思ったら行動しません。
③がないと②でした行動がうまくいかなかった時に次の行動につながないかもしれません。
こう考えると楽観はとても努力の必要な貴重な状態な気がしました。
嫌なことがあった時には、①②③へのそれぞれへの質問として
①きちんと受け止めているか?
②自分には何ができるか?
③どうしたらうまくいったと言えるのか?
を考えていこうと思いました。
2つ目は、
性格についての遺伝子と環境の関係がより広くになったことです。
性格は遺伝子と環境のどちらで決まるのか?
という質問は答えが遺伝子でも環境でも、
遺伝子だから環境だから自分にはどうしようもないという
個人の努力ではどうしようもない運命的な考え方が含まれているような気がしました。
この本の中で性格は遺伝子と環境の相互作用の面があることが紹介されています。
環境によって遺伝子が発現するかしないかが変わるという考えです。
これは遺伝子として持っていても環境がなければ、遺伝子が発現しないことであり、
環境がそろっていても、遺伝子がなければ発現しないということです。
この考えに従って自分の遺伝子の発現率を上げたいなら、
さまざまな環境に自分を置くことでその確率を上げられるということです。
ついつい同じ店や道に行ってみたくなってしまう私としては、
新しい環境に行く理由がさらに増えたように感じました。
最後の3つ目は、
ポジティブとネガティブの黄金比を一つの基準にできるようになったことです。
この本で紹介されている黄金比は
ポジティブ:ネガティブ = 3:1
この黄金比から考えたことは、
①ネガティブが1であることからネガティブは必要なもの
②普段ポジティブをそれだけ多く考えられているか?
の2つでした。
①については、
ネガティブなことを減らすことによって、
ポジティブが少なくて済むようにするようにするというよりは、
ネガティブは起こることを前提として受け入れることが大切だと思いました。
また、ネガティブなことが起こらないのも、
変化を避けて新しいことに挑戦していないのではないかと
考える1つのきっかけになるように感じました。
②については、
ぱっと思い浮かべるとネガティブなことが多く、
ポジティブなことが少ないような気がした。
(最近はありがとうを心掛けているので以前よりはポジティブが増えてはいると思う。)
ネガティブが起こることを前提として、
ポジティブなことを見つけたり、
どちらにも解釈できるものはポジティブに捉えるようにして、
貯ポジティブをしていこうと思いました。
全体的な感想としては、
事実は変わらないとしても解釈の仕方で、
自分の世界は変わるし脳も変化するそう感じさせる1冊でした。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『脳科学は人格を変えられるか?』を使ってみてはいかがで
しょうか?