『科学の発見』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『科学の発見』です。
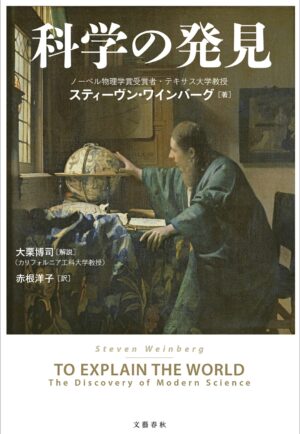
1 読んだら役に立つと思われる人
・哲学から科学への歴史を知りたい人
・天動説と地動説の移り変わりを知りたい人
・美しさを重視した詩的な考えから実験などの観察や実験など、実証をするようになるまでの考え方の移り変わりを知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①観察と実験の言葉について改めて考えたこと
②天動説と地動説が個人の世界と共通しているように感じたこと
③この本で出てくる考え方が考えの幅を広げてくれたこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
前回に引き続き以前に使った『知的戦闘力を高める 独学の技法』で紹介されて、
興味を持ったので読んでみることにしました。
4 本を使っての変化
この本を読んで大きく3つの変化がありました。
まず、1つ目は、
観察と実験の認識がより明確になったことです。
観察 基本的に手を加えずありのままを捉えようとすること
実験 自分の考えた結果が正しいのかをそれを証明するのに必要なことを能動的に設定して確かめること
自分の日常生活で観察をして推測をすることはあったが、
推測した結果に対してそれを確かめる為の実験をしていないことに気がついた。
実際に実験するか別として
仮に実験で証明するとしたら?
という質問は
・人
・時代や時間
・環境
などを能動的考えるに質問として使えるように思いました。
2つ目は、
天動説と地動説の考え方が個人の考え方の変化に似ているような気がしました。
天動説は地球が動いているのではなく、
太陽や月が地球の回っているという考え方です。
人に当てはめると
これがどこか自分が世界の中心でその回りの世界があるという
自分は変わらないが回りは変わるといったような
どこか自己中心的な考え方があるように感じました。
地動説は、地球が動いているので、
太陽や月が回って見えるという考え方です。
地動説がなかなか認められなかった理由として、
地球が動いているという実感がなかったことです。
電車の中から外の風景を見ているようなもので、
電車(地球)は動いているが自分が動いている実感がなかったので、
回りが動いていると思ってしまっていたようです。
もし、電車の急ブレーキのように地球の動きが遅くなったら、
みんな実感として地球が動いていことに気づけたのでしょう。
人にあてはめると
地動説に気付くということは、
天動説的に回りの人が自分を中心に何かしてくれるという考えが
うまくいかないことが多いと気づき、
それならば、自分が動くことを選択することだ思いました。
(愚痴ばかりいって自分が動かない人は、
どこかおかしいと気づいているけれど自分中心主義(天動説)を捨てられない人)
最後の3つ目は、
この本の中に出てくる考え方と今の考えを照らし合わせることで
考え方の幅を広げることができたことです。
この本の最初に出てくる哲学者の考えたことは、
万物のものになる物質は何か?というもの。
水だという人もいれば空気だという人もいて、
そこには証明という概念はない。
これは今の私の感覚だと無責任なように感じる。
無責任に感じる理由を考えると言うことには根拠がいると
無意識に思っていることに気付きました。
会話に根拠を求めれば、
それが正しいのか?というストッパーがかかり、
話さすないでおくことが増えるのも当然だに思えました。
日常のたわいのない話であれば、
根拠というリミッターをはずしてもいいと思いました。
ほかには、この本の中で出てくるモデルでは、
まずは簡単なものをベースにして考えています。
円なら正円、速度なら等速、平均速度など。
とっかかりとしてはいいのでしょうが、
正円でなく楕円、等速でなく速度が変化することを
いつのまにか考えの外にしてしまいます。
正円や等速がいつの間にか正しいことが前提になってしまい、
本当は楕円や速度が変化するのに
そのずれは他の手法を加えることで観察された現象と一致するように、
複雑な補正処理をしていくことが紹介されています。
このことから、ある程度の説明が出来たから補正で対処したが、
その補正が複雑になっているならば、
根本的な考え方が間違っているのではないか?
と一旦立ち止まって考えることが大切に思えました。
全体的な感想としては、
科学は世界を説明しようとする試みであることを改めて感じました。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『科学の発見』を使ってみてはいかがでしょうか?