『和のふるまい 言葉事典』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『和のふるまい 言葉事典』です。
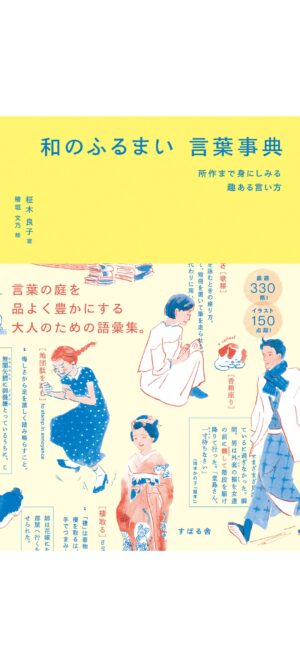
1 読んだら役に立つと思われる人
・和を感じる言葉、ふるまいを感じたい人
・イラストから視覚的な和を感じたい人
・同じことを別の言葉でいうヒントが欲しい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①読めば意味はわかるが普段は使わない言葉に触れられたこと
②少し古く感じる言葉からそこにある価値観に触れられたこと
③イラストにより言葉がより明確に理解できたこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
江戸時代のしぐさなど今はしていないけれど、
昔に存在したしぐさや言葉を通じてそこにある価値観を感じたいと思ったからです。
4 本を使っての変化
この本を使っての3つの大きな変化がありました。
まず、1つ目は
和服があったからこの言葉があると感じられたことです。
いくつか例をあげると
・袖に忍ばせる
(着物はポケットがない代わりに袖や胸元、帯の中などしまえるスペースがあちこちにある)
・懐手する
寒さをしのぐために、両手を(着物の)衣の内側の懐に入れている格好。
・はだける
衿(えり)や裾などの衣服の前が開いて、体の一部があらわになること
・抜き衣紋
「衣紋」は着物の衿の名称。衿を後ろへ引き下げて首すじが出るように、着物を着ること。
これらを通じて感じたことは、
1つなぎの布を帯で固定するというシンプルさゆえの自由さと隙(いい意味での)を感じました。
袖などにものをしまったり、両手を衣の内側に入れるのは、
形の整えられた洋服では難しく、仮にしたとしても見た目が様にならない。
はだけるや抜き衣紋は、
個人的には精神的な隙が和服の物理的な隙として連動しているように感じました。
2つ目は、上品なしぐさのヒントに触れられたことです。
いくつかの例をあげると
・歩くときに小股で歩く
・指股が開くと子供っぽい印象に。中指と人さし指をそろえると品よくみえる
・飲み物を飲むときなどに脇を軽く締める
・拾うものの横に立ち、足を一歩引き、膝を曲げて、低く腰を落とす。(背筋を伸ばしたまま)
これらに共通していそうなことを考えてみました
・大きな動作をしない
・無意識でできる行動とは思えない
無意識でできている人が仮にいるとすれば、
身近にいる人がたまたまお手本となる人がいて、
それを真似できた人だけのような気がしました。
ということは、
上品なしぐさを知ってそれを取り入れて
無意識でできるように繰り返した結果の現われのように感じました。
そして、上品なしぐさを心掛けることが
いつの間にかその人自身がまとう上品になっていくような気もしました。
最後の3つ目は、
言葉とイメージを1対1にしていることに気付いたことです。
ほお杖をつくと聞いて
どんなイメージが浮かんだでしょうか?
(ちょっと思い浮かべてください。)
私が思い浮かんだのは、
片手で頬杖をつきながらマウスで画面操作をしているイメージでした。
この本では、これ以外の帆杖が紹介されています。
①片頬を支えた手にもう片方の手も添える、大人かわいい頬杖
②重ねた両手の甲に顎をちょこんと乗せ、相手の話に聞き入っている感じの頬杖
③結んだ手を顎先に軽く当て、もう一方の手は肘を支えるL字ポーズ、思案している風の頬杖
④有名な「太宰治の頬杖」を思わせるポーズで、ラフな雰囲気ながらも知性を感じさせる頬杖
(てのひらで顔を支えて、反対の腕を曲げて無造作に置いている)
⑤アイドル風のポートレートで定番のポーズ、両頬を両手指を曲げながら包むような頬杖
と私の思い浮かべた頬杖とは大分違うものが紹介されています。
1つの言葉に対して複数のイメージを持つことで、
どのイメージに近いのかを質問しながら相手と共有してくのも
楽しい会話をするヒントになるように思えました。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『和のふるまい 言葉事典』を使ってみてはいかがでしょうか?