『自分のアタマで考えよう――知識にだまされない思考の技術』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『自分のアタマで考えよう――知識にだまされない思考の技術』です。
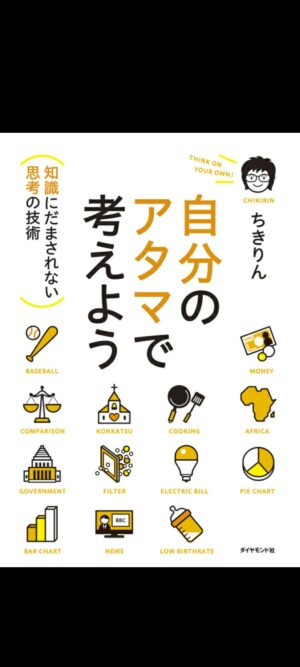
1 読んだら役に立つと思われる人
・考えるって何と質問されて何も思い浮かばない人
・自分なりの考えるがあるが他の人の考えるについて知りたい人
・考えたことが良い面、悪い面のどちらかに片面になりがちな人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①自分の考えるがぼんやりとしていたことがわかったこと
②考えたことと思っていたことが自分の既存の知識に合う情報を集めていただけだったことに気づいたこと
③良い面と悪い面の両面を考えることで成功の幅が広がったこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
以前に読んでいた本の中でおすすめ本として紹介されて気になったので、使ってみました。
4 本を使っての変化
自分で考えたことが他の人から聞いた知識を
自分の考えであるかのように話しているだけで
実は自分の考えでなかったことに気づいたときははっとしました。
他の人がそう言っているからそうなのだろうと思ってしまうのは、
考える労力を省略出来てとても楽ではあります。
けれど、いざ自分にしかできない判断をする時に、
他の人はこう言っているからと決めるようでは、
なんだか自分の人生を生きているのかふと疑問に思ってしまいます。
「本使いさんはどうしたいの?」
「何が好きなの?」
と個人的なことを聞かれるのが苦手な理由がこの本を読んでわかった気がしました。
それはきっと自分で考えることをあまりしてこなかったからだと思います。
この本の中では、
自分でもっている知識にそれにあった情報を集めることで考えたと思ってしまう例をあげています。
その対策として出した結論が良い面あるいは悪い面に偏っていたら両面を考えることを提案しています。
この本での考えるの定義は
インプットをアウトプットに変換することとしています。
「私は考えた」=「私はあるインプットをもとに、なんらかの結論を出した。ある考えに至った」
とも言っています。
この定義に従うと頭の中で同じことがぐるぐるして結局何も結論がでない場合は、
考えているには入らないことになります。
そうならない為に、結論を出すために必要な意思決定のプロセスの大切さを説明しています。
必要そうな情報をまず集めようではなく、これの結論を出すの必要なことを決めて、
その情報を集めて結論を出すというごくごく当たり前だけれど忘れがちなことが述べられています。
自分なりのこの本を読んでの結論は、
・知識は他の人の考えたことの結論で考えた時代や人によるバイアスがかかっていることがあることを心にとめておく
・知識を出すプロセスを学ぶことによって、自分の考えを出すヒントにする
・自分の考えが偏らないように良い面、悪い面の両方を出すようにする
・どんな結論を出したいのか?それを出すのに重要なことを具体的にしておくs
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『自分のアタマで考えよう――知識にだまされない思考の技術』を使ってみてはいかがでしょうか?