『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』です。
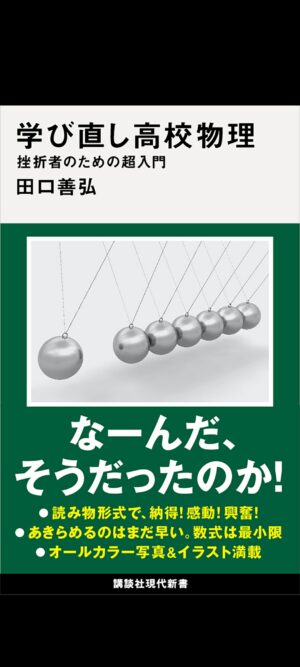
1 読んだら役に立つと思われる人
・高校で物理を学んでいて物理をもう一度やってみたい人
・高校で物理を習っていなくいが興味のある人
・日常の生活の中にある物理を知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①物理の単位などがそれに関係のある人の名前が使われているのを知れたこと
②原因や理論が違っていても最初に結果があっていた人の名前が使われつづけていること
③日頃当たり前と思っている前提を改めて考え直すきっかけになったこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
ラジオ番組を聞いていてこの本が紹介されていて、
物理的な考え方は持てれば新しい考え方をするヒントになるのでは?と思ったからです。
4 本を使っての変化
物理というと理論が確立していて変わることはないイメージだが、
結論はあっていたが理由や過程が違うことがあることが紹介されている。
これには推定でもいいので自分なりの結論を出しておくことの大切さを感じた。
物理には、しばしば〇〇の2乗という表現が登場する。
これに接して普段生活していると自分が直線的に物事を考えているように感じた。
2乗という考え方が物事が急速に変化する可能性の一端を表現しているような気がした。
2乗が出てくる法則の式に静電気力に関するクーロンの法則に
F(静電気力)=k(クーロンの法則の比例定数)*q1*q2(各点電荷の電気量)/r^2(各点電荷間の距離)
というものがある
これをどこか人間の関係性についての式のようにも感じられた。
特に距離が大きくなるほど力が弱くなるのは、
物理的な距離があると人間関係も小さくなり疎遠になることを表現しているような気がした。
また、この静電気力は同電荷(+と+、-と-)だと反発し、異電荷(+と-)ひきつけあう。
これも同電荷で反発は同族嫌悪や異電荷は自分に無いものに心惹かれるといった
人間の関係を示しているように感じて興味深かった。
もともとのこの本の読んだきっかけの新しい考えのヒントになりそうなことは、
物理的な慣性の法則などを精神的な表現をするのに使えるのではないか?
例えば、精神的な慣性の法則は習慣といえそうに感じた。
わかりやすさ、つたわりやすさの向上の手段として物理的な考えを加えていこうと思った。
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』を使ってみてはいかがでしょうか?