『「探究」する学びをつくる』を使う
こんにちは、本使いです!
今回使うのは『「探究」する学びをつくる』です。
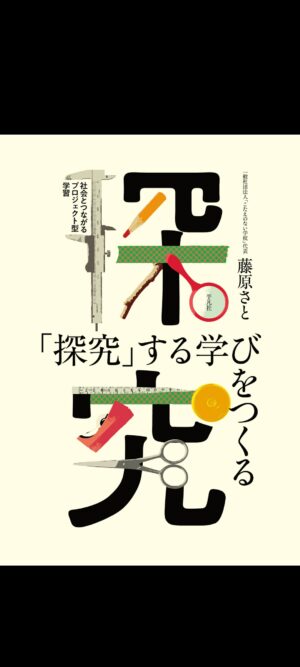
1 読んだら役に立つと思われる人
・探求について考えたい人
・プロジェクト型学習を知りたい人
・なぜ学校に行かなければいけないのか?への1つの答えを知りたい人
2 この本の個人的に良かったところ3点
①目的をプロジェクトとして考えるようになったこと
②探求の言葉を見つけられたこと
③「エレメント」の考えに触れたこと
3 読んだきっかけ
この本を読んだきっかけは、
次に読む本を探していた時に探求の言葉にひかれて
使ってみることにしました。
4 本を使っての変化
この本を使っての変化は3つあります。
この本を使っての1つ目の変化は、
プロジェクトを目的と目標の間に入れるとしっくりきたことでした。
自分の中で目的と目標の距離がしっくりしていなかったことに気づきました。
目的は立てそれについての目標を立ててもうまくいかないことがしばしば。
目標を目的に近すぎると目標が遠すぎてモチベーションが保てない。
しかし、現実に近すぎるとこれをすれば最終的な目的に近づくのか?でモチベーションが保てない。
この本を読んだ後の目的とプロジェクトと目標の関係は
目的 最終的なゴール
プロジェクト 目的に必要なことを分解したそれぞれの到達点
目標 プロジェクトのそれぞれの進行度の目安(プロジェクトが変わればなくなったり、増えたりと変更が起きるのも普通)
以前の目標は目標を立てたらそれを達成できないと
そこで終わっていたがプロジェクトで考えると
プロジェクトから見て、この目標が必要なのか?もっと目標を簡単にした方がいいのか?
と目標に対して変更をすることで目的へのモチベーションをつなげるように思えた。
2つ目の変化は、
探求という言葉はわからないこと→わかることに変え、
他のわかっていないことやわかったことで発生したなぞに、
再度わからないこと→わかることを繰り返すこと。
この定義の探求ということを自分はしてこなかったと思った。
何かに答えが出たらそこで1区切りをつけてそれ以上知ろうとしていなかった。
自分なりの答えが出た時に一度立ち止まって、
・他にわかっていなことはないか?
・わかったことで新しくわからないことがないか?
を考え、わからないことを楽しむように心がけようと思った。
3つ目の変化は、
この本の中の「エレメント」という言葉によって感じたことだ。
「エレメント」の定義は
「自分の才能と情熱が出会う場所」=「自分にとって、それをするのが自然に感じられること」
そして、エレメント探しは2方向への旅である。
「あなたの中にあるものを探る内なる旅」と「外の世界での機会を探す外界での旅」
誰もが2つの世界に2つの世界に住んでいる。
人は内なる世界を通してしか、外の世界を知ることはできない。
と書かれている。
特に最後の1行は考えさせられるものがあった。
内なる世界を通してしかの部分は、
物理的に同じ外の世界ならを相手も同じものを見ていると錯覚してしまいがちだが、
相手の世界を通しての外の世界なので必ずしも一致しないということを考えさせられた。
また、この2方向の旅の仕方は最後の1文を考慮すると
「あなたの中にあるものを探る内なる旅」
→内面だけの旅
「外の世界での機会を探す外界での旅」
→内面を通しての外界の旅
どちらにも内面は関わっているので、変化をしたいのなら内面を変えた方が影響が大きいように感じた。
(もちろん、外界を変える方が簡単でわかりやすい利点はある。)
5 おわりに
いかがでしたでしょうか?
気になった方は
『「探究」する学びをつくる』を使ってみてはいかがでしょうか?